平山夢明論と映画「ダイナー」
2019年7月7日 趣味
平山夢明という作家をご存じだろうか。代表作は推理作家協会賞を受賞した「独白するユニバーサル横メルカトル」や大藪春彦賞を受賞し今月5日から映画が公開された「ダイナー」など。怪談実話や都市伝説系のショートストーリーの書き手としても知られ、作品の傾向から善く「鬼畜系作家」と評されることもある。氏への誉め言葉として「どうかと思うが、面白い」というフレーズがあるが、今回はそうした留保抜きに平山作品の特徴を述べていきたい。
平山小説の特色として、その形容のセンスがある。①簡潔で当を得た描写②敢えて冗長な比喩の2点から解説していきたい。
平山小説は非常に映像的な文体だと言われる。それは起きていることを淡々と描写するハードボイルドタッチなどという次元ではなく、描写や比喩が具体的で一発で頭の中に映像が浮かぶからだ。例えば「ダイナー」の序盤、ブルドッグの描写。
「…ホワイトアスパラのような歯が…」
これだけで「小ぶりで先が尖っている」「乳白色」「つやつやと光沢がある」様が伝わる。
他にも「けだもの」という短編で、狼男の自動治癒の描写はどうか。
「…肩口の傷はジッパーが盛り上がるようにして閉じ、腹に開いた穴はひしゃげた弾をぷっと吐き出した…」
前節の描写では治癒にかかる時間(おそらく数秒)、後節の描写では弾が飛び出す速度感も伝わってくる。
傑作選の解説によれば、氏は小説を書く際頭の中に白い画面をイメージするという。その画面の中でキャラクターを動かしその描写を筆に起こすのだと。氏は学生時代映画製作に打ち込んでおり、映画に造詣が深い。文筆業の出発点がゴミビデオ100本評というのも頷ける話だ。
ここからは敢えて逆の「冗長な表現」を挙げていきたい。再び「ダイナー」にて、オオバカナコが下拵えをするシーン。
「…死んだ犬の睾丸のようなナッツを延々剥きながら…」
冗長な表現にも効果はあって、場面場面のイメージを代弁する働きを持っている。ここでは明日をも知れぬ身である主人公に死のイメージを重ね合わさる。他にも不潔さを想起させるものとして「牛乳を拭いて日向で干した雑巾」などの表現もある。
媒体には媒体ごとの強みがある。私は平山作品は小説でしか表現できないものだと思うのだ。これまで平山作品はいくつか映像化が試みられてきたが、どれも低予算でひっそり終わった。鬼畜鬼畜と評されても、平山作品は実は残酷度やキチガイ度は穏当ではないか。他の鬼畜小説家、友成純一のような「女性器が分離して羽が生え、吸血モモンガとして追いかけてくる」話はないのだ(こんなの書くのは友成先生か伊藤潤二ぐらい)。寧ろ映画監督で言えばイーライロスのように「最低な目に遭うが最後は因果応報に落ち着く」オーソドックスな構造の話が多い。そしてそれらを支えるのが氏の筆力なのだ。
なんでまあ、藤原竜也主演でそれなりの予算とはいえ、映画化自体無理だったと思うんですよね。だって小説の面白さが伝わんねーもん。魅力的な設定と人物、印象的なシーンを継ぎはぎすれば2時間映画に仕上がるという肝の腐った脚本はこの際許すよ。
でもさ、「裏世界では人命は軽い」っていう大前提を映像的に崩しちゃダメでしょ。ヤクザの金を奪ったカウボーイの処刑、ボンベロの超人的身体能力の下りを削ったせいでさ、「ここは人殺し専用のダイナー。皿の置き方ひとつで消されることもある」って文句に説得力がさらさらない。蜷川パパ譲りのくっどい舞台芸術と服装も明らかに悪影響。「まぼろしの市街戦」みたく、精神異常者集団がコスプレOFF会開いてるようにしか見えませんよ。
おまけに初めての殺人シーンで頭の破裂どころか血すら見せないとはね…。興行の都合上R指定つかないマイルドな殺人表現にしたかったんですか?なら傾奇者殺し屋アクションの成功作たる「ジョンウィック」のように武器を銃にする工夫はしなかったの?枝切りハサミ持って「うわあい、殺しちゃうぞー」とはしゃぐ心底下らない演出よりは、よっぽどましな画になったと思うんですがね。
ラスト20分の籠城バトルは結構楽しめましたが、原作(或いはコミカライズ)の乾いたタッチのピカレスクものを期待したら大変損します。一言で言えば蜷川監督が名作を私物化してひり出した駄作。
代わりのおススメとしては、ニコラス・ウィンディング・レフン作品。「ドライヴ」が有名ですが、「プッシャー三部作」こそが平山ワールドの忠実な映像化です。
平山小説の特色として、その形容のセンスがある。①簡潔で当を得た描写②敢えて冗長な比喩の2点から解説していきたい。
平山小説は非常に映像的な文体だと言われる。それは起きていることを淡々と描写するハードボイルドタッチなどという次元ではなく、描写や比喩が具体的で一発で頭の中に映像が浮かぶからだ。例えば「ダイナー」の序盤、ブルドッグの描写。
「…ホワイトアスパラのような歯が…」
これだけで「小ぶりで先が尖っている」「乳白色」「つやつやと光沢がある」様が伝わる。
他にも「けだもの」という短編で、狼男の自動治癒の描写はどうか。
「…肩口の傷はジッパーが盛り上がるようにして閉じ、腹に開いた穴はひしゃげた弾をぷっと吐き出した…」
前節の描写では治癒にかかる時間(おそらく数秒)、後節の描写では弾が飛び出す速度感も伝わってくる。
傑作選の解説によれば、氏は小説を書く際頭の中に白い画面をイメージするという。その画面の中でキャラクターを動かしその描写を筆に起こすのだと。氏は学生時代映画製作に打ち込んでおり、映画に造詣が深い。文筆業の出発点がゴミビデオ100本評というのも頷ける話だ。
ここからは敢えて逆の「冗長な表現」を挙げていきたい。再び「ダイナー」にて、オオバカナコが下拵えをするシーン。
「…死んだ犬の睾丸のようなナッツを延々剥きながら…」
冗長な表現にも効果はあって、場面場面のイメージを代弁する働きを持っている。ここでは明日をも知れぬ身である主人公に死のイメージを重ね合わさる。他にも不潔さを想起させるものとして「牛乳を拭いて日向で干した雑巾」などの表現もある。
媒体には媒体ごとの強みがある。私は平山作品は小説でしか表現できないものだと思うのだ。これまで平山作品はいくつか映像化が試みられてきたが、どれも低予算でひっそり終わった。鬼畜鬼畜と評されても、平山作品は実は残酷度やキチガイ度は穏当ではないか。他の鬼畜小説家、友成純一のような「女性器が分離して羽が生え、吸血モモンガとして追いかけてくる」話はないのだ(こんなの書くのは友成先生か伊藤潤二ぐらい)。寧ろ映画監督で言えばイーライロスのように「最低な目に遭うが最後は因果応報に落ち着く」オーソドックスな構造の話が多い。そしてそれらを支えるのが氏の筆力なのだ。
なんでまあ、藤原竜也主演でそれなりの予算とはいえ、映画化自体無理だったと思うんですよね。だって小説の面白さが伝わんねーもん。魅力的な設定と人物、印象的なシーンを継ぎはぎすれば2時間映画に仕上がるという肝の腐った脚本はこの際許すよ。
でもさ、「裏世界では人命は軽い」っていう大前提を映像的に崩しちゃダメでしょ。ヤクザの金を奪ったカウボーイの処刑、ボンベロの超人的身体能力の下りを削ったせいでさ、「ここは人殺し専用のダイナー。皿の置き方ひとつで消されることもある」って文句に説得力がさらさらない。蜷川パパ譲りのくっどい舞台芸術と服装も明らかに悪影響。「まぼろしの市街戦」みたく、精神異常者集団がコスプレOFF会開いてるようにしか見えませんよ。
おまけに初めての殺人シーンで頭の破裂どころか血すら見せないとはね…。興行の都合上R指定つかないマイルドな殺人表現にしたかったんですか?なら傾奇者殺し屋アクションの成功作たる「ジョンウィック」のように武器を銃にする工夫はしなかったの?枝切りハサミ持って「うわあい、殺しちゃうぞー」とはしゃぐ心底下らない演出よりは、よっぽどましな画になったと思うんですがね。
ラスト20分の籠城バトルは結構楽しめましたが、原作(或いはコミカライズ)の乾いたタッチのピカレスクものを期待したら大変損します。一言で言えば蜷川監督が名作を私物化してひり出した駄作。
代わりのおススメとしては、ニコラス・ウィンディング・レフン作品。「ドライヴ」が有名ですが、「プッシャー三部作」こそが平山ワールドの忠実な映像化です。



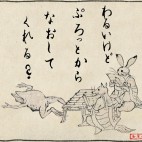
コメント