映画『21世紀の資本』とドキュメンタリー私論
2020年5月27日 映画 コメント (2)
前置きの前置き
トマ・ピケティの経済論について話をする気はありません。僕には経済の教養がないし、著作も2冊しか目を通していないからです。飽くまで(僕個人の)ドキュメンタリー論に即して話をします。
あらすじ
「貧乏人は子々孫々金持ちになれない」。封建主義からフランス革命、新大陸時代、帝国主義に2度の大戦、冷戦とグローバリズム…300年の歴史を辿りながら示される、資本と労働の関係。格差の広がる構造「r>g」が行きつく先、ピケティの説く21世紀の姿とは…。
※ ※ ※ ※ ※
前置き
ドキュメンタリー映画ってプロパガンダでなんぼじゃねえすか?
…って持論ぶち上げから話を始めます。
映画は書籍に比べ、説明には向いてません。図像や概念等の抽象情報を提示し辛い、尺の都合で情報量に上限がある、改訂・参考文献の提示といった情報の付加が出来ない。
一方で情動に訴える力は非常に強い。2時間暗闇に拘束され、理解や思考が追いつかぬまま光と音の洪水に包まれる。洗脳の道具として最適なんですね。
映画は歴史的に大衆向きの媒体でした。無学な人でも、物語やニュースを受け取れる。何十時間の読書と反芻を経ずとも、90分でマインドセットが切り替わる。(「国民の創生」のように危険と隣り合わせですが…)
特にドキュメンタリーは多く社会問題を扱います。議論に先立ち、「そもそも知らない」状態が最悪な以上、多くの人に届き心に残るものでなければならない。誇張・偏りを前提としながらも観客は感動し(或いは反発し)、本を読む・調べる一歩となる…これがドキュメンタリー映画の役割だと考えてます。
ここで「効果的」なドキュメンタリーの4要件を提示します。プロパガンダドキュメンタリーの王様、マイケルムーアの作品群にはこれらが必ず含まれています。
①分かり易さ:情報の末節を省き、論旨を簡略化すること。
アニメーションやテロップで情報を整理すること。
記録映像をサンプリング的に使うことでユーモア、恐怖、皮肉を感じさせ、絶えず観客を飽きさせぬこと。
②弱者、被害者:これも特定の個人を心掛けること。ニュースやワイドショーでも絶対に数字よりインタビューを重視してるやん?行きつく先が24時間テレビのアレ。
③強者=敵:ニュース映像、新聞写真、インタビュー、とにかく特定の個人として認識させること。
目線の泳ぎ、口元、応答の逡巡、佇まいや声色などに編集を総動員して「悪意or疚しさ」を演出すること。
④展望:社会問題に対し、観客各人でも明日からできる小さな抵抗へと細分化していくこと。
※ ※ ※ ※ ※
それで、映画『21世紀の資本』はどうだったか。一言にすると薄味なんですが、先述したフレームワークに沿って説明していきます。
①分かり易さ
めっちゃ上手い。
原作も決して難解な本ではありません。700pの多くは、膨大なデータ集積による資本・労働関係の歴史的実証に過ぎません(それ自体が前代未聞だけど)。
映画ではそれを更に簡略化。経済理論の話と各国比較を丸ごと削り、世界全体の潮流を編年体に並べることにより、万人が理解できる形になりました。ピケティ本人が監修をしているので、エッセンスも損なわれない。
更に「高慢と偏見」「怒りの葡萄」「レミゼラブル」などの引用もあり観ていて飽きが来ない。インタビューにある通り、社会科学とアートの言語が違うことをちゃんと意識してるんですね。封建時代から戦後50年代までの下りはスゲー良いです。
②弱者、被害者
とピケティが言うように、(本に比べて)映画は一般向けです。なのに今作は1980年代までの歴史編とそれ以後の現代編、どちらもモンタージュ・フラッシュカットで繋いでいる。そのため現代の貧困さえも歴史の一幕であるように見える。ここは対照的に、観客の焦燥を煽る作りにすべきでは?
インタビューではなくポップカルチャーの引用で済ませるにしても、そのチョイスも問題。「シンプソンズ」「ファミリーガイ」「エリジウム」…。アニメにSFと、抽象度が一段階上なんすよ。「わたしは、ダニエルブレイク」や「フロリダプロジェクト」のように、先進国の今まさにある貧困をリアルに扱った映画は山とあるのにさあ…。
③強者=敵
特定の敵が居ない。グローバル企業、資本家、投資家…。どれも抽象的なお金持ちを表す言葉に過ぎない。フェイスブックの名前は出てもザッカーバーグの顔も出なければ、ロゴも映さない。持続して観客の悪感情を引き受ける被写体が出てこない。
…いや、何度も金持ち出てきてましね。ピケティ始めとした教授連中です。これ、冗談じゃないですよ。ドキュメンタリー監督の森達也は「ドキュメンタリーは撮り手のセルフドキュメントである」、と語っています。
「左派気取ってんならテメェが私財寄付しろや」とは言いません。でも、本とドキュメンタリー映画は違うんですよ。本の著者は限りなく透明でいられても、ドキュメンタリー映画では語り手の情報量は凄まじい。教授連中は皆仕立ての良い服を着て、歯並びは綺麗、炭水化物太りはしておらず、一流大学の大教室や落ち着いた私邸の一室でインタビューを受けている。誰がどう見ても勝ち組側なんです。
ここでムーアを引き合いに出します。彼は「ボウリングフォーコロンバイン」で富豪になった後も、野球帽にTシャツのラフな格好で取材に臨む。実態はどうあれ、俺たち側に「見える」んです。そういったセルフイメージに無自覚であるのは、ドキュメンタリー映画として欠陥です。
④展望
一切なし。原作に同じく、ピケティはいくつかの解決策を提示します。タックスヘイヴンで税逃れをする企業には収益先市場から課税し制裁を科す、累進資産課税と相続税を富裕層から厚く取る、民主主義で資本主義に対抗する…。んで、俺らには何が出来んの?
何度も名を挙げますが、ムーアは違う。銃社会→規制の緩さ→銃弾小売への圧力、独裁主義→ボトムアップで対抗→労組・学生運動・SNS、と(矮小化のきらいはあるが)小目標の設定をしてくれている。
「脳死してんな、自分で考えろ」の反論は通用しません。重ねて言いますが、何故なら媒体特性がピケティの言うように違うんですから!より大衆向けなのに、結論を本と同じ抽象度に落とし込んでどうするんですか!?
※ ※ ※ ※ ※
お上品止まりなのが返す返す残念です。中流層はケツに火が付いている実感が持てないし、貧困層は打つ手なしと立ち尽くすばかりでしょう。
ウォルマートに立ち寄り、TVディナー片手にFOXニュースを付け、スマホでGAFAのサービスを利用する…映画館を出た我々は、そんな日常に帰るしかないのでは。
トマ・ピケティの経済論について話をする気はありません。僕には経済の教養がないし、著作も2冊しか目を通していないからです。飽くまで(僕個人の)ドキュメンタリー論に即して話をします。
あらすじ
「貧乏人は子々孫々金持ちになれない」。封建主義からフランス革命、新大陸時代、帝国主義に2度の大戦、冷戦とグローバリズム…300年の歴史を辿りながら示される、資本と労働の関係。格差の広がる構造「r>g」が行きつく先、ピケティの説く21世紀の姿とは…。
※ ※ ※ ※ ※
前置き
ドキュメンタリー映画ってプロパガンダでなんぼじゃねえすか?
…って持論ぶち上げから話を始めます。
映画は書籍に比べ、説明には向いてません。図像や概念等の抽象情報を提示し辛い、尺の都合で情報量に上限がある、改訂・参考文献の提示といった情報の付加が出来ない。
一方で情動に訴える力は非常に強い。2時間暗闇に拘束され、理解や思考が追いつかぬまま光と音の洪水に包まれる。洗脳の道具として最適なんですね。
映画は歴史的に大衆向きの媒体でした。無学な人でも、物語やニュースを受け取れる。何十時間の読書と反芻を経ずとも、90分でマインドセットが切り替わる。(「国民の創生」のように危険と隣り合わせですが…)
特にドキュメンタリーは多く社会問題を扱います。議論に先立ち、「そもそも知らない」状態が最悪な以上、多くの人に届き心に残るものでなければならない。誇張・偏りを前提としながらも観客は感動し(或いは反発し)、本を読む・調べる一歩となる…これがドキュメンタリー映画の役割だと考えてます。
ここで「効果的」なドキュメンタリーの4要件を提示します。プロパガンダドキュメンタリーの王様、マイケルムーアの作品群にはこれらが必ず含まれています。
①分かり易さ:情報の末節を省き、論旨を簡略化すること。
アニメーションやテロップで情報を整理すること。
記録映像をサンプリング的に使うことでユーモア、恐怖、皮肉を感じさせ、絶えず観客を飽きさせぬこと。
②弱者、被害者:これも特定の個人を心掛けること。ニュースやワイドショーでも絶対に数字よりインタビューを重視してるやん?行きつく先が24時間テレビのアレ。
③強者=敵:ニュース映像、新聞写真、インタビュー、とにかく特定の個人として認識させること。
目線の泳ぎ、口元、応答の逡巡、佇まいや声色などに編集を総動員して「悪意or疚しさ」を演出すること。
④展望:社会問題に対し、観客各人でも明日からできる小さな抵抗へと細分化していくこと。
※ ※ ※ ※ ※
それで、映画『21世紀の資本』はどうだったか。一言にすると薄味なんですが、先述したフレームワークに沿って説明していきます。
①分かり易さ
めっちゃ上手い。
原作も決して難解な本ではありません。700pの多くは、膨大なデータ集積による資本・労働関係の歴史的実証に過ぎません(それ自体が前代未聞だけど)。
映画ではそれを更に簡略化。経済理論の話と各国比較を丸ごと削り、世界全体の潮流を編年体に並べることにより、万人が理解できる形になりました。ピケティ本人が監修をしているので、エッセンスも損なわれない。
更に「高慢と偏見」「怒りの葡萄」「レミゼラブル」などの引用もあり観ていて飽きが来ない。インタビューにある通り、社会科学とアートの言語が違うことをちゃんと意識してるんですね。封建時代から戦後50年代までの下りはスゲー良いです。
②弱者、被害者
(映画は)「21世紀の資本」の読者以外のさまざまな人々、もっと広範な人々に届けるのにうってつけ
とピケティが言うように、(本に比べて)映画は一般向けです。なのに今作は1980年代までの歴史編とそれ以後の現代編、どちらもモンタージュ・フラッシュカットで繋いでいる。そのため現代の貧困さえも歴史の一幕であるように見える。ここは対照的に、観客の焦燥を煽る作りにすべきでは?
インタビューではなくポップカルチャーの引用で済ませるにしても、そのチョイスも問題。「シンプソンズ」「ファミリーガイ」「エリジウム」…。アニメにSFと、抽象度が一段階上なんすよ。「わたしは、ダニエルブレイク」や「フロリダプロジェクト」のように、先進国の今まさにある貧困をリアルに扱った映画は山とあるのにさあ…。
③強者=敵
特定の敵が居ない。グローバル企業、資本家、投資家…。どれも抽象的なお金持ちを表す言葉に過ぎない。フェイスブックの名前は出てもザッカーバーグの顔も出なければ、ロゴも映さない。持続して観客の悪感情を引き受ける被写体が出てこない。
…いや、何度も金持ち出てきてましね。ピケティ始めとした教授連中です。これ、冗談じゃないですよ。ドキュメンタリー監督の森達也は「ドキュメンタリーは撮り手のセルフドキュメントである」、と語っています。
「左派気取ってんならテメェが私財寄付しろや」とは言いません。でも、本とドキュメンタリー映画は違うんですよ。本の著者は限りなく透明でいられても、ドキュメンタリー映画では語り手の情報量は凄まじい。教授連中は皆仕立ての良い服を着て、歯並びは綺麗、炭水化物太りはしておらず、一流大学の大教室や落ち着いた私邸の一室でインタビューを受けている。誰がどう見ても勝ち組側なんです。
ここでムーアを引き合いに出します。彼は「ボウリングフォーコロンバイン」で富豪になった後も、野球帽にTシャツのラフな格好で取材に臨む。実態はどうあれ、俺たち側に「見える」んです。そういったセルフイメージに無自覚であるのは、ドキュメンタリー映画として欠陥です。
④展望
一切なし。原作に同じく、ピケティはいくつかの解決策を提示します。タックスヘイヴンで税逃れをする企業には収益先市場から課税し制裁を科す、累進資産課税と相続税を富裕層から厚く取る、民主主義で資本主義に対抗する…。んで、俺らには何が出来んの?
何度も名を挙げますが、ムーアは違う。銃社会→規制の緩さ→銃弾小売への圧力、独裁主義→ボトムアップで対抗→労組・学生運動・SNS、と(矮小化のきらいはあるが)小目標の設定をしてくれている。
「脳死してんな、自分で考えろ」の反論は通用しません。重ねて言いますが、何故なら媒体特性がピケティの言うように違うんですから!より大衆向けなのに、結論を本と同じ抽象度に落とし込んでどうするんですか!?
※ ※ ※ ※ ※
お上品止まりなのが返す返す残念です。中流層はケツに火が付いている実感が持てないし、貧困層は打つ手なしと立ち尽くすばかりでしょう。
ウォルマートに立ち寄り、TVディナー片手にFOXニュースを付け、スマホでGAFAのサービスを利用する…映画館を出た我々は、そんな日常に帰るしかないのでは。


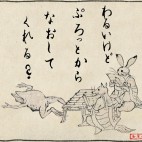
コメント
この映画は実際に見た人間ですが、おっしゃる通り政策論だけでは政権交代に期待する前提で、現状どれだけ富裕層を優遇してもトランプや安倍政権が勝ち続けていて実現可能性が低いのが問題ですね。
かといってデモを起こしたところで今はSNSなどでイメージを悪く操作する力も政権側にあり、本当に打つ手なしに思ってしまいます。