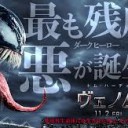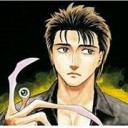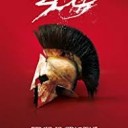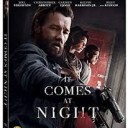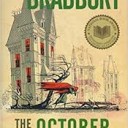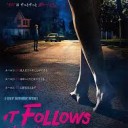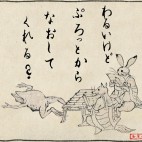「目…肺…すい臓…ひと息に食らい尽くす。」
2018年11月3日
https://www.youtube.com/watch?v=xLCn88bfW1o
テレビ記者のエディは取材のさ中、シンビオートと呼ばれる地球外生命に寄生された。体に巣食った「ヴェノム」は脳内で命令を下し出す。エディは理性では抗いながらも、邪悪な力に魅せられていく…。映画「ヴェノム」はそんなダークな映画ではない。
宣伝文句は英語では"The world has enough heros."(もうヒーローには飽きたろ?)、日本版では「世界を変えるのは、いつだって『最悪』だ」とあるように、明らかにダーク方向を志向している。宣伝と実際の乖離の理由を考えるに、配給のソニー映画の意向なのだろーなーと思い到る。だって、「スパイダーマン3」のヴェノムの雰囲気そのままだもん。
サムライミ版「スパイダーマン3」では、シンビオート=ヴェノムは最初ピーターに寄生した。ヴェノムの毒気に充てられたピーター=スパイダーマンは悪名高いクソダサダンスを踊るも
https://www.youtube.com/watch?v=nVmXsBNfwHY
宿主の高潔さにいら立ったヴェノムは宿主をエディに変更。その憎悪を増幅させ今度はスパイダーマンの敵になる…というのがスパイダーマン3だった。愛嬌のかけらもない邪悪な存在としてヴェノムが描かれていたので、スパ3はコミックファンの受けが悪い。
ところがソニーはヴェノムにご執心だった。ヴェノム単体映画、ゆくゆくはシリーズ化したい…と考え「アメイジングスパイダーマン」をリブートするも興行振るわず。一方マーベルスタジオがアイアンマン以降の映画を成功し続けスパイダーマンの映画化権利を買い戻したため、アメスパシリーズそのものが消滅した。ところがソニーはヴェノムを諦めず、遂に映画化。10年越しである。今作、マーベル側はノータッチ(OPクレジットでもasociated with=協力扱い)だが、ソニー側は「ゆくゆくはスパイダーマンとコラボするかもなー」とすり寄っている始末である。
今作ヴェノムは宣伝にあるようなジキル/ハイドジャンルではない。では何かというと…「寄生獣」だ。ひょんなことから宇宙生物に寄生された男。寄生体の生態構造ゆえに相即不離の関係になった二人は、互いの在り方に不満を感じつつも徐々に影響を受け合い始め、人間でもエイリアンでもない個体へと成長を遂げていく。
「腹減った!エサくれ!」「スゲー力だろホラ」「そうかお前はあの女が好きなのか」と無駄口を叩いていたヴェノムが、やがて「俺たちははぐれ者同士だ、だからこそ、二人でならやつに勝てる」と信頼を寄せて来る。これミギーでしょう!!山崎貴のクソゴミ映画なんてなかったんだ!「ミギー!お前…ここに残ってたのか…!」(最終話より)
本作はダークさがスポイルされたせいか批評家受けは悪い。とはいえルーベン・フライシャー監督が「ゾンビランド」で見せたジャンルものへの拘りとブラックユーモアもあって興行成績は上々。寄生獣における後藤さんこと、アンチヒーロー「カーネイジ」は続編に出るようだ。ダークな雰囲気のヴェノムは、その時に期待しよう。
テレビ記者のエディは取材のさ中、シンビオートと呼ばれる地球外生命に寄生された。体に巣食った「ヴェノム」は脳内で命令を下し出す。エディは理性では抗いながらも、邪悪な力に魅せられていく…。映画「ヴェノム」はそんなダークな映画ではない。
宣伝文句は英語では"The world has enough heros."(もうヒーローには飽きたろ?)、日本版では「世界を変えるのは、いつだって『最悪』だ」とあるように、明らかにダーク方向を志向している。宣伝と実際の乖離の理由を考えるに、配給のソニー映画の意向なのだろーなーと思い到る。だって、「スパイダーマン3」のヴェノムの雰囲気そのままだもん。
サムライミ版「スパイダーマン3」では、シンビオート=ヴェノムは最初ピーターに寄生した。ヴェノムの毒気に充てられたピーター=スパイダーマンは悪名高いクソダサダンスを踊るも
https://www.youtube.com/watch?v=nVmXsBNfwHY
宿主の高潔さにいら立ったヴェノムは宿主をエディに変更。その憎悪を増幅させ今度はスパイダーマンの敵になる…というのがスパイダーマン3だった。愛嬌のかけらもない邪悪な存在としてヴェノムが描かれていたので、スパ3はコミックファンの受けが悪い。
ところがソニーはヴェノムにご執心だった。ヴェノム単体映画、ゆくゆくはシリーズ化したい…と考え「アメイジングスパイダーマン」をリブートするも興行振るわず。一方マーベルスタジオがアイアンマン以降の映画を成功し続けスパイダーマンの映画化権利を買い戻したため、アメスパシリーズそのものが消滅した。ところがソニーはヴェノムを諦めず、遂に映画化。10年越しである。今作、マーベル側はノータッチ(OPクレジットでもasociated with=協力扱い)だが、ソニー側は「ゆくゆくはスパイダーマンとコラボするかもなー」とすり寄っている始末である。
今作ヴェノムは宣伝にあるようなジキル/ハイドジャンルではない。では何かというと…「寄生獣」だ。ひょんなことから宇宙生物に寄生された男。寄生体の生態構造ゆえに相即不離の関係になった二人は、互いの在り方に不満を感じつつも徐々に影響を受け合い始め、人間でもエイリアンでもない個体へと成長を遂げていく。
「腹減った!エサくれ!」「スゲー力だろホラ」「そうかお前はあの女が好きなのか」と無駄口を叩いていたヴェノムが、やがて「俺たちははぐれ者同士だ、だからこそ、二人でならやつに勝てる」と信頼を寄せて来る。これミギーでしょう!!山崎貴のクソゴミ映画なんてなかったんだ!「ミギー!お前…ここに残ってたのか…!」(最終話より)
本作はダークさがスポイルされたせいか批評家受けは悪い。とはいえルーベン・フライシャー監督が「ゾンビランド」で見せたジャンルものへの拘りとブラックユーモアもあって興行成績は上々。寄生獣における後藤さんこと、アンチヒーロー「カーネイジ」は続編に出るようだ。ダークな雰囲気のヴェノムは、その時に期待しよう。
秋アニメ折り返し
2018年11月13日・ゾンビランドサガ
評価更に爆上げ。
序盤の下手さ演出が凄い。80年代を経験した(秋元おニャン子・小泉今日子「何ってったってアイドル」・岡田有希子自殺)日本アイドルと世界の若手スターの違いは、上達の過程を愛でるか完成度の高さを称賛するかにある。ハルヒライブが伝説なのは、演奏のとちり声のかすれで高校生らしさまで作り込まれていたから。
残念ながら以降のアイドル・学生バンドものは現実のCD展開見据え始めから完成度の高いものが多かった。おんマスライブお前らだよ。彼女らの個人的葛藤の解消やグループ不和の解決によって成長を表現していたが、「俺らが応援することでアイドルが成長していく」快感はそこに生じなかった。
で、ゾンビランドサガ。中途半端なパフォーマンスを見せられることのシラケ・居た堪れなさがきちんと伝わってくる。だからこそ6話シリアス回がストーリーのみならず納得できる。
ここまで真剣にアイドルを考察したアニメなのだから、労働関係のブラックさ・営業企画の「仕掛け」・疑似恋愛問題も掘り下げるのかな。そしたら伝説になる。
・グリッドマン
ただただ面白い。
作られた世界メタネタは今更なので、どうツイストしてくるか楽しみだね。円谷監修なのだからそこ絡めた何かがあると嬉しい。
・色づく世界の明日から
説明不足。3話で主人公の色盲が提示され「だからイケメンの絵に惚れたのか」と分かったものの、「なら魔法と色の関係は?」とか「そもそも魔法の原理は?」と謎が湧いてくる。直接説明するアニメが良いとは勿論思わんが、些末な疑問を吹き飛ばす画や話がある訳でなし…。
加えてドラマが余りに薄い。「スリービルボード」とは言わんが、PA成功作の「花咲くいろは」ぐらいは無理なのか。トラブルに面することで、主要キャラの違った性格が見えて来るというのはエンターテイメントの常道のハズ。今作はタダの良い子ちゃんたちが質朴な学生生活を送ってるだけだよ。アクションもエロもギャグもない地味アニメで話が退屈なのは致命的。
・やがて君になる
所作・構図の妙は原作読んで確認したが、光の効果や動きの上手さはアニメならではだね。胸にもたれかかった先輩の髪をしゅるりと手櫛で梳くシーンが本当に官能的でね!これもうね!
・風が強く吹いている
三浦しをん原作あって、キャラの作り・関係性が絶妙。
とはいえ、スポーツものとしてどうなのか。3話で高校同期のライバルが「お前こんなレベルと一緒で情けなくないのか!」と言ってくるが正論にしか聞こえない。マネーボールやジャイアントキリングやルーズベルトゲームみたいに、前時代的なスポ根を廃して科学的統計的に勝つなら分かる。でも彼らの練習風景から本業陸上部に勝つロジックがまるで見えてこない。「選ばれたやつしか走っちゃいけないのか」って言ってるけど、ズブの素人チームが4月から始めて年明けの箱根で勝つ方がよっぽど「選ばれ」てるから!
片手間やっつけの奴らが全国で結果残すとしたら、それは鼻もちならない才能論なのでは。
・ジョジョ5部
ムーディーブルース登場回でアバッキオの同僚の死を先に描く改変はナイス。原作で唐突だった「舟は2隻あった!!」も鍵番号と舟番号の乖離で伏線貼ってあるのでわかり易い。アバッキオへの勧誘シーンしかり、アニオリ小ネタが光る。
・ダグ&キリル
サンライズさん、これ何時タイバニになるの…(絶望
本当にこのオチャラケで完走するのか?
・転スラ
異世界転生もの唯一の魅力と言えば終わりだが、チートパラメータでトントン拍子に進んで影響力伝播・地歩固めが際限なく広がっていく快感の甘美さ。これ嫌いな男の子居ないでしょ。
・ゴブスレ
1話のショックありきだが、未熟な冒険者がフラグ発言するたびに後の惨劇を予想してヒヤヒヤする。けどウェスクレイヴンだったら定期的に人殺してサービスくれたよなあ…と要らんこと考えたりもする。
評価更に爆上げ。
序盤の下手さ演出が凄い。80年代を経験した(秋元おニャン子・小泉今日子「何ってったってアイドル」・岡田有希子自殺)日本アイドルと世界の若手スターの違いは、上達の過程を愛でるか完成度の高さを称賛するかにある。ハルヒライブが伝説なのは、演奏のとちり声のかすれで高校生らしさまで作り込まれていたから。
残念ながら以降のアイドル・学生バンドものは現実のCD展開見据え始めから完成度の高いものが多かった。おんマスライブお前らだよ。彼女らの個人的葛藤の解消やグループ不和の解決によって成長を表現していたが、「俺らが応援することでアイドルが成長していく」快感はそこに生じなかった。
で、ゾンビランドサガ。中途半端なパフォーマンスを見せられることのシラケ・居た堪れなさがきちんと伝わってくる。だからこそ6話シリアス回がストーリーのみならず納得できる。
ここまで真剣にアイドルを考察したアニメなのだから、労働関係のブラックさ・営業企画の「仕掛け」・疑似恋愛問題も掘り下げるのかな。そしたら伝説になる。
・グリッドマン
ただただ面白い。
作られた世界メタネタは今更なので、どうツイストしてくるか楽しみだね。円谷監修なのだからそこ絡めた何かがあると嬉しい。
・色づく世界の明日から
説明不足。3話で主人公の色盲が提示され「だからイケメンの絵に惚れたのか」と分かったものの、「なら魔法と色の関係は?」とか「そもそも魔法の原理は?」と謎が湧いてくる。直接説明するアニメが良いとは勿論思わんが、些末な疑問を吹き飛ばす画や話がある訳でなし…。
加えてドラマが余りに薄い。「スリービルボード」とは言わんが、PA成功作の「花咲くいろは」ぐらいは無理なのか。トラブルに面することで、主要キャラの違った性格が見えて来るというのはエンターテイメントの常道のハズ。今作はタダの良い子ちゃんたちが質朴な学生生活を送ってるだけだよ。アクションもエロもギャグもない地味アニメで話が退屈なのは致命的。
・やがて君になる
所作・構図の妙は原作読んで確認したが、光の効果や動きの上手さはアニメならではだね。胸にもたれかかった先輩の髪をしゅるりと手櫛で梳くシーンが本当に官能的でね!これもうね!
・風が強く吹いている
三浦しをん原作あって、キャラの作り・関係性が絶妙。
とはいえ、スポーツものとしてどうなのか。3話で高校同期のライバルが「お前こんなレベルと一緒で情けなくないのか!」と言ってくるが正論にしか聞こえない。マネーボールやジャイアントキリングやルーズベルトゲームみたいに、前時代的なスポ根を廃して科学的統計的に勝つなら分かる。でも彼らの練習風景から本業陸上部に勝つロジックがまるで見えてこない。「選ばれたやつしか走っちゃいけないのか」って言ってるけど、ズブの素人チームが4月から始めて年明けの箱根で勝つ方がよっぽど「選ばれ」てるから!
片手間やっつけの奴らが全国で結果残すとしたら、それは鼻もちならない才能論なのでは。
・ジョジョ5部
ムーディーブルース登場回でアバッキオの同僚の死を先に描く改変はナイス。原作で唐突だった「舟は2隻あった!!」も鍵番号と舟番号の乖離で伏線貼ってあるのでわかり易い。アバッキオへの勧誘シーンしかり、アニオリ小ネタが光る。
・ダグ&キリル
サンライズさん、これ何時タイバニになるの…(絶望
本当にこのオチャラケで完走するのか?
・転スラ
異世界転生もの唯一の魅力と言えば終わりだが、チートパラメータでトントン拍子に進んで影響力伝播・地歩固めが際限なく広がっていく快感の甘美さ。これ嫌いな男の子居ないでしょ。
・ゴブスレ
1話のショックありきだが、未熟な冒険者がフラグ発言するたびに後の惨劇を予想してヒヤヒヤする。けどウェスクレイヴンだったら定期的に人殺してサービスくれたよなあ…と要らんこと考えたりもする。
セックス・ピストルズ~漫画と映像と時間表現と~
2018年11月18日
グダグダ語ってますが、要はジョジョ7話のアクション表現はダサいっていう話です。
https://magiclazy.diarynote.jp/201711052300504107/
このブログで度々名前を出すが、名著Understanding comicsの4章"Time Frame”にこんな評論がある。「漫画はコマとコマの間の時間、1コマに流れる時間を自在に操れる表現媒体である」と。同じ画でも効果音・視覚効果で一瞬でも十数秒にでも感じさせられ、普通に発話すれば10秒以上かかる台詞も「一瞬の感情の発露」として受け取らせることも出来る。
これは原作のジョジョに顕著だ。キャラクターの深掘りをアクションの中で荒木氏は行う。回想シーンを挟まずとも、口調・思想から人となりが伝わる。絵的な興奮とドラマ的な面白さが両立してるからこそ、ジョジョはオンリーワンなバトル漫画なのだ。
では、ジョジョのバトルシーンは映像化不可能なのか?違う。漫画文法を用いて成功した実写映画が一つある。ザックスナイダーの最高傑作、「スリー・ハンドレッド」だ。
https://www.youtube.com/watch?v=HdNn5TZu6R8
https://www.youtube.com/watch?v=D0xSqLrG-ow
彼はフランクミラーの原作に多大なリスペクトを払った。アクションシーンに悉く原作の構図を配置し、静止画の連続の間を埋めるように早送りを配置。スロー→早回し→スロー→早回しは以後のアクション演出を一変させた。この手法も万能ではないのだが、殊今回のジョジョに関する限り使う必要性はあった。何故なら銃という速さが命の武器なのだから。
https://www.nicovideo.jp/watch/sm34184033
で、5部7話の銃撃シーン。ピストルズが出現して以降時間の流れがずっと等速なのは本当にダレるし、構成も上手くない。ミスタやピストルズの台詞はアクションの中に配する必然性がないのだ。スタンドへの激励は事前に済ませられるし、ピストルズ同士の連携も食事シーンでの掛け合いで済ませられた筈。発砲→弾道変更→着弾という本来一瞬で終わり、だからこそ見ごたえのあるシーケンスを30秒だらだら流すのだから台無しになって当然だ。
とはいえ、david production制作のジョジョも5部まで続いているのだから、この電気紙芝居方式も支持されているのだろう(アニメファンなのか、ジョジョ信者かは別にして)。この調子ならエアロスミスも期待できそうにない。ナランチャがグッダグダ長台詞をくっちゃべっているのに何時になっても相手に辿り着かない、亀より遅いスタンドになるのだろうな。
https://magiclazy.diarynote.jp/201711052300504107/
このブログで度々名前を出すが、名著Understanding comicsの4章"Time Frame”にこんな評論がある。「漫画はコマとコマの間の時間、1コマに流れる時間を自在に操れる表現媒体である」と。同じ画でも効果音・視覚効果で一瞬でも十数秒にでも感じさせられ、普通に発話すれば10秒以上かかる台詞も「一瞬の感情の発露」として受け取らせることも出来る。
これは原作のジョジョに顕著だ。キャラクターの深掘りをアクションの中で荒木氏は行う。回想シーンを挟まずとも、口調・思想から人となりが伝わる。絵的な興奮とドラマ的な面白さが両立してるからこそ、ジョジョはオンリーワンなバトル漫画なのだ。
では、ジョジョのバトルシーンは映像化不可能なのか?違う。漫画文法を用いて成功した実写映画が一つある。ザックスナイダーの最高傑作、「スリー・ハンドレッド」だ。
https://www.youtube.com/watch?v=HdNn5TZu6R8
https://www.youtube.com/watch?v=D0xSqLrG-ow
彼はフランクミラーの原作に多大なリスペクトを払った。アクションシーンに悉く原作の構図を配置し、静止画の連続の間を埋めるように早送りを配置。スロー→早回し→スロー→早回しは以後のアクション演出を一変させた。この手法も万能ではないのだが、殊今回のジョジョに関する限り使う必要性はあった。何故なら銃という速さが命の武器なのだから。
https://www.nicovideo.jp/watch/sm34184033
で、5部7話の銃撃シーン。ピストルズが出現して以降時間の流れがずっと等速なのは本当にダレるし、構成も上手くない。ミスタやピストルズの台詞はアクションの中に配する必然性がないのだ。スタンドへの激励は事前に済ませられるし、ピストルズ同士の連携も食事シーンでの掛け合いで済ませられた筈。発砲→弾道変更→着弾という本来一瞬で終わり、だからこそ見ごたえのあるシーケンスを30秒だらだら流すのだから台無しになって当然だ。
とはいえ、david production制作のジョジョも5部まで続いているのだから、この電気紙芝居方式も支持されているのだろう(アニメファンなのか、ジョジョ信者かは別にして)。この調子ならエアロスミスも期待できそうにない。ナランチャがグッダグダ長台詞をくっちゃべっているのに何時になっても相手に辿り着かない、亀より遅いスタンドになるのだろうな。
『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』が今年ワースト級
2018年11月23日
カノン7部と伝記は読んだものの、指定教科書や舞台劇本には手を出してないにわかです。知識不足からの誤謬があればご指摘下さい。
①粗筋
オブスキュラスを宿す少年、クリーデンスは生きていた。「グリンデルバルド側に引き込まれては手遅れになる。君にしか出来ない仕事だ」とダンブルドアに依頼され、ニュートはパリに飛ぶ。
一方のクリーデンスはフリークショーの見世物だった蛇女ナギニを連れ、自分の出自を探す旅に出ていた。獄を脱したグリンデルバルドは彼に近づき、純血の名家レストレンジの墓に真実があると告げる。
地下墓地に集まる一同。その奥では純血主義者の集会が開かれていた。グリンデルバルドは会衆に向け演説を打つ。マグルは傲慢で争いを好む、きっと先の大戦を越える大災厄を齎すだろう。それを防ぐためにも、魔法使いはマグルを飼わなければならない、と。止めようとする闇祓いに対し、グリンデルバルドは選別の炎で壁を作る。忠誠を誓うものは焼かれずに越えられる。クリーデンスが、更にはマグル寄りのクィニーすら軍門に下っていく。パリを火の海にするのは阻止できたものの、失ったものは大きかった…。
古城に佇むクリーデンスとグリンデルバルド。本当の出自が明かされる。クリーデンスの本名はアウレリウス・ダンブルドア。ダンブルドア一門の裔だったのだ。
②マグル問題:構造上の類似作品
この映画の欠点は大きく分けて二つ。マグルの中年ジェイコブを連れていることと、グリンデルバルドの魅力がないこと。
先ずマグル問題を語ろう。
ニュート「クィニーを探しに行こう、君も一緒だ!」
ジェイコブ「よし!!」
意 味 が 分 か ら な い 。
前作「ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅」を一言で説明しよう。「メン・イン・ブラック」だ。本来一般人は「あちら」の世界を知るのは禁じられ、不慮の事態では記憶を消される。一般人とあちら側の人間がやむを得ず手を組み、事件解決後に記憶を消すことを前提の旅に出る…。同じプロットなのだ。壊れたニューヨークの街全体を魔法で覆って記憶を消すラストの展開、MIB2の自由の女神像のニューラライザーフラッシュと全く同じ構造なのにお気づきだろうか?
③マグル問題:物語上の必然性
で、前作で記憶を消された筈のジェイコブが再び出る。クイニ―と恋仲なのはまだ分かる。だがクリーデンスを探す旅に連れていく理由が寸毫たりとも存在しない。前作には後々記憶を消すという理由づけがまだあった。戦間期という時代設定ゆえ、魔法使いとマグルを階層社会に見立て(別離が運命付けられた)身分違いの悲恋を描くという演出上の意味もあった。今作にはねえよ!記憶消せよ!
ジェイコブが語るには、「忘却術が勝手に解けた」とのこと。ああ、これが後で効いて来るのか!と観客は当然思う。伊賀の里の破邪瞳術だったり、魔法の構築は出来ないが解体は超一流の劣等生だったり、異能の力を打ち消す幻想殺しだったりするのか…!何もない。活躍もせずぼさーっと突っ立ってるだけ。
極めつけは純血主義者の集会だろう。いわばKKKの首吊り集会に黒人が紛れているようなものだ。この状況でクイニ―が「愛してるわ」って頭おかしいんじゃねえか?
④グリンデルバルド問題:演出の下手さ
脚本ではなく、演出上の問題もある。グリンデルバルドが世界の命運を分けるほどの敵に見えない。集会のシーンで未来の映像を彼は見せる。時代設定が戦間期であり、「純血主義」者が「排斥・管理すべき」民衆の危険性を訴えるのだから、当然ヒトラーを想起させる。その筈なのに、ジョニデの演説にはまるで引き込まれない。
何もヒトラー式の演説をまるまるコピーしろとは言わない。だが「言葉巧みな余り看守が3度変えられ、終いには舌を切られた」ほどの能弁家なのだから、説得力あるシーンが必要だ。「ザ・マスター」「ウィンストン・チャーチル」のように、やり込めようと待ち構えていた敵までもが、彼の言葉の力に脱帽するシーン一つあれば良かったのだが。
これが無いとどうなるか。それに負ける人間が間抜けに見える。主人公側のクイニ―が闇堕ちするシーンは本来悲しい筈だ。だがグリンデンバルドに説得力がないから「恋愛脳の馬鹿女が騙されたのね」としか見えない。
⑤グリンデルバルド問題:悪役キャラの差別化
何故グリンデルバルドに拘るのか?彼がヴォルデモートとは違うタイプの悪役であることが、カノンで既に示されているからだ。
7部「死の秘宝」の中で、グリンデルバルドはダンブルドアの莫逆の友であったと明かされる。彼の純血主義に若き日のダンブルドアは傾きかけ、それがため妹が死ぬ事故が起きた。あのダンブルドアですら影響を受ける、そんな心理タイプの悪役として納得できる演出つけてくれよ…。淡々と喋りやがってお前は笠智衆かよ…。
⑥結びに
一言。幼稚。
隣に座っていた中年のご婦人連れはハリポタファンなのか、魔法動物が出て来る度カワイイワァーと楽しまれていました。そんな優しい観方が出来る人にだけおススメです。
①粗筋
オブスキュラスを宿す少年、クリーデンスは生きていた。「グリンデルバルド側に引き込まれては手遅れになる。君にしか出来ない仕事だ」とダンブルドアに依頼され、ニュートはパリに飛ぶ。
一方のクリーデンスはフリークショーの見世物だった蛇女ナギニを連れ、自分の出自を探す旅に出ていた。獄を脱したグリンデルバルドは彼に近づき、純血の名家レストレンジの墓に真実があると告げる。
地下墓地に集まる一同。その奥では純血主義者の集会が開かれていた。グリンデルバルドは会衆に向け演説を打つ。マグルは傲慢で争いを好む、きっと先の大戦を越える大災厄を齎すだろう。それを防ぐためにも、魔法使いはマグルを飼わなければならない、と。止めようとする闇祓いに対し、グリンデルバルドは選別の炎で壁を作る。忠誠を誓うものは焼かれずに越えられる。クリーデンスが、更にはマグル寄りのクィニーすら軍門に下っていく。パリを火の海にするのは阻止できたものの、失ったものは大きかった…。
古城に佇むクリーデンスとグリンデルバルド。本当の出自が明かされる。クリーデンスの本名はアウレリウス・ダンブルドア。ダンブルドア一門の裔だったのだ。
②マグル問題:構造上の類似作品
この映画の欠点は大きく分けて二つ。マグルの中年ジェイコブを連れていることと、グリンデルバルドの魅力がないこと。
先ずマグル問題を語ろう。
ニュート「クィニーを探しに行こう、君も一緒だ!」
ジェイコブ「よし!!」
意 味 が 分 か ら な い 。
前作「ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅」を一言で説明しよう。「メン・イン・ブラック」だ。本来一般人は「あちら」の世界を知るのは禁じられ、不慮の事態では記憶を消される。一般人とあちら側の人間がやむを得ず手を組み、事件解決後に記憶を消すことを前提の旅に出る…。同じプロットなのだ。壊れたニューヨークの街全体を魔法で覆って記憶を消すラストの展開、MIB2の自由の女神像のニューラライザーフラッシュと全く同じ構造なのにお気づきだろうか?
③マグル問題:物語上の必然性
で、前作で記憶を消された筈のジェイコブが再び出る。クイニ―と恋仲なのはまだ分かる。だがクリーデンスを探す旅に連れていく理由が寸毫たりとも存在しない。前作には後々記憶を消すという理由づけがまだあった。戦間期という時代設定ゆえ、魔法使いとマグルを階層社会に見立て(別離が運命付けられた)身分違いの悲恋を描くという演出上の意味もあった。今作にはねえよ!記憶消せよ!
ジェイコブが語るには、「忘却術が勝手に解けた」とのこと。ああ、これが後で効いて来るのか!と観客は当然思う。伊賀の里の破邪瞳術だったり、魔法の構築は出来ないが解体は超一流の劣等生だったり、異能の力を打ち消す幻想殺しだったりするのか…!何もない。活躍もせずぼさーっと突っ立ってるだけ。
極めつけは純血主義者の集会だろう。いわばKKKの首吊り集会に黒人が紛れているようなものだ。この状況でクイニ―が「愛してるわ」って頭おかしいんじゃねえか?
④グリンデルバルド問題:演出の下手さ
脚本ではなく、演出上の問題もある。グリンデルバルドが世界の命運を分けるほどの敵に見えない。集会のシーンで未来の映像を彼は見せる。時代設定が戦間期であり、「純血主義」者が「排斥・管理すべき」民衆の危険性を訴えるのだから、当然ヒトラーを想起させる。その筈なのに、ジョニデの演説にはまるで引き込まれない。
何もヒトラー式の演説をまるまるコピーしろとは言わない。だが「言葉巧みな余り看守が3度変えられ、終いには舌を切られた」ほどの能弁家なのだから、説得力あるシーンが必要だ。「ザ・マスター」「ウィンストン・チャーチル」のように、やり込めようと待ち構えていた敵までもが、彼の言葉の力に脱帽するシーン一つあれば良かったのだが。
これが無いとどうなるか。それに負ける人間が間抜けに見える。主人公側のクイニ―が闇堕ちするシーンは本来悲しい筈だ。だがグリンデンバルドに説得力がないから「恋愛脳の馬鹿女が騙されたのね」としか見えない。
⑤グリンデルバルド問題:悪役キャラの差別化
何故グリンデルバルドに拘るのか?彼がヴォルデモートとは違うタイプの悪役であることが、カノンで既に示されているからだ。
7部「死の秘宝」の中で、グリンデルバルドはダンブルドアの莫逆の友であったと明かされる。彼の純血主義に若き日のダンブルドアは傾きかけ、それがため妹が死ぬ事故が起きた。あのダンブルドアですら影響を受ける、そんな心理タイプの悪役として納得できる演出つけてくれよ…。淡々と喋りやがってお前は笠智衆かよ…。
⑥結びに
一言。幼稚。
隣に座っていた中年のご婦人連れはハリポタファンなのか、魔法動物が出て来る度カワイイワァーと楽しまれていました。そんな優しい観方が出来る人にだけおススメです。
難解ホラー『イット・カムズ・アット・ナイト』長文評
2018年11月26日
①粗筋
山奥の邸宅で過ごすポール一家。「病気」にかかった祖父を安楽死させ、外ではガスマスクをし夜は厳重な戸締りをかけることで外部からの感染を防いでいた。
ある夜、侵入者が現れる。ウィルと名乗る男は家族のために水を求めていると告げ、共存を求める。ウィル一家が家畜を連れてきたことでより豊かになった生活。だが開放厳禁の内扉が深夜開いていたことから、コミュニティーに亀裂が走り出す…。
②何かがこの夜をやって来る
総指揮・主演はデビュー作「ギフト」で高い評価を受けたジョエル・エドガートン、制作スタジオは「ムーンライト」他先鋭的な作品を生み出し続けるA24。アメリカでは去年公開され批評家の受けは良い今作。最大の論点は「it/それ」とは何なのか?だろう。
初手ネタバレをしておくと、「何か」は一度も出てこないし正体も明かされない。何度も「病気」という語は出され、廊下に掛かった絵がブリューゲルの「The Triumph of Death」であるように、何らかの感染症であるとは言われる。だが私はこの「病気=it」はメタファーであり、見た目通り受け取るべきではないと考える。理由を幾つか提示していこう。
③itは病原体なのか?
・防疫ガバ
酷評レビューで多く見られたもの。会話を多少交わしただけのウィル相手にマスクを外し、ポリタンクに直に口つけて水を飲む。煮沸した湯で外出着を消毒することもしない。
防毒マスク・手袋・赤い内扉は物理的に病原体を排除するものではなくお前を拒絶するという意思表示を意味するものと私は考える。だからこそポールは、ウィルに信頼を寄せる間はマスクを外し、疑い出してからはマスクを着けるのだ。
・感染者を見せない
ポール一家の祖父バッドは冒頭で死ぬが、血色の悪さは老人としては普通だ。ウィル一家の息子アンドリューは感染するが、魘されだして以降は一度たりとも画面に顔を見せない。肌が真っ黒に壊死しボコボコと膨れる感染者のイメージは、ポール一家の息子トラヴィスの夢を通じてしか描かれない。
・感染者は「病死しない」
これがメタファーであると考える最大の理由。バッドは冒頭で安楽死させられた。森にかけこみ感染したと思しき飼い犬は、ポールとウィルの手で殺された。ネタバレになるが、ウィル一家3人も感染者だと判断され処刑された。今作、誰一人として病によって死ぬ者は居ないのだ。
④Itの正体と二つの映画
https://gaga.ne.jp/itcomesatnight/(シークレットレビューの項)
http://news.livedoor.com/article/detail/15630730/
公式サイトみたいに高尚ぶってはぐらかすのも愚かなので、私なりの解釈をはっきり言語化しよう。Itとは「悪(と他者が認識するもの)」である。見終わって浮かんだ映画が2本ある。「ヴィレッジ」と「イット・フォローズ」だ。
「ヴィレッジ」は森の奥に怪物が居る、だから小さな村の中で無垢に生きて行こうという話だった。大人たちが演じる怪物を振り切り駆け抜けた少女は、森の果てに広がる現代社会を見て呆然とする…という話だ。あの怪物と今作のitは似たものではないだろうか?
トラヴィスが何度もバッドの夢を見るように、思い入れのある祖父だったのだろう。ゆえに、義父であり異なる父権たる彼をポールは疎ましく感じたのかもしれない。アンドリューはトラヴィスと違い従順な子供ではない。夢遊病で内扉を開ける(=別の価値観を家の中に招く)彼を、ポールは感染者と見做した。ウィルの妻キムは若く性的魅力に溢れる。トラヴィスは彼女の胸や腿に目を遣り、夫婦の情交を盗み聞きしている。性に目覚めてしまった自分の息子まで、ポールは処分する。ラストシーン、ポール夫妻は互いを見つめる。その瞳は黒く染まり感染者の兆候を示している。我が子に手をかけてしまった自責と憎しみで、二人は視線を交わし合う。
では、Itは無くすべきものなのだろうか?A24の大ヒット作「イットフォローズ」のスタッフは、今作に大きくかかわっている。「イットフォローズ」の監督デビットロバートミッチェルは、ついてくるものは「愛と生と死」であると説明している。人と関わって生きていく上で、決して逃れ得ぬもの。だからこそ覚悟して、共に歩んでいかねばならぬ他者性。ヴィレッジの元ネタはブラッドベリの短編「びっくり箱」なのだが、閉鎖社会を飛び出し外部を知った少年が叫ぶシーンで小説は閉幕する。”僕は死んだ。死んだんだ。死ぬのはうれしい。死ぬというのは、なんてすてきなことだろう!”
⑤メタファーの傑作たち
ここまで書いてきてどうかと思うが、作品評価としては興味深い(interesting)が面白い(entertaining)とは言えないに落ち着く。理由を説明するために、メタファー映画の傑作を紹介しよう。
50年代、宇宙人映画はアメリカに忍び込んだアカを意味していた。ロメロの「ナイトオブザリビングデッド」は黒人差別、「ゾンビ」は商業主義の奴隷を意味していた。これらの映画が優れているのは、裏の意味を読み解かずとも映像的に楽しめるところだ。怪獣が核の象徴だと分からずとも、本田猪四郎の「ゴジラ」は涙が出るほど素晴らしい。「イットフォローズ」だって、ババアが摺り足でにじる画がクソ怖い。
⑥「見せない」映画
視覚的に怪物として現出させろ、という短絡的な発想ではない。ブツを見せないホラーはいくらでもある。「ねじの回転」は性的不満で苛立つオールドミスの狂奔ぶりが凄まじい。「ブレアウィッチプロジェクト」は後年「幽霊の出ないホラー」として批判されるが、異常な雰囲気で一行が散々に互いを罵り合うからこそ、あの映画は怖い。「10・クローバー・フィールド・レーン」は後半エイリアンパニックものに変わるが、前半の密室劇では「宇宙人が居ると言い張るだけの狂人ではないか?」というスリラーになっているのだ。
上述した通り、怪物が出ない以上はサイコスリラー・サスペンスにならざるを得ない。「イット・カムズ・アット・ナイト」はそこの作りが上手くないのだ。
⑦サイコスリラー
例えばItの恐怖を煽るのは森の風景や悪夢ではなく、人間の狼狽ぶりにするとかさ。
サイコもので見せ場になる筈の決裂過程も上手くない。赤い扉を開けた犯人捜しをあっさり済ませたのはもったいない。そこは互いの家族の人格否定を滲ませながらネチネチ粗探しようぜ!
あっさり「安全のために互いの居住空間を分けよう」としたのも味気ない。表面上は仲直りしていても会話の時に顔の位置をずらしたり、共有物を布越しに触れる描写を積み重ねた上で、決定的に断絶しなきゃ。このジャンルは胃がきしんでナンボでしょ!
⑧結びに
本作は本国での一般客受けがクソ悪く、日本公開は一年遅れた。ミニシアター限定の「意識高い系」映画に分類されるが、ホラーとしてそこそこのレベルにあるのでもっと知られるべき作品だと思う。高尚ぶって言辞を弄したり、やっぱクソ映画だ死ねーと罵倒したり。何だかんだ語る幅のある、コスパの高さは間違いない。
山奥の邸宅で過ごすポール一家。「病気」にかかった祖父を安楽死させ、外ではガスマスクをし夜は厳重な戸締りをかけることで外部からの感染を防いでいた。
ある夜、侵入者が現れる。ウィルと名乗る男は家族のために水を求めていると告げ、共存を求める。ウィル一家が家畜を連れてきたことでより豊かになった生活。だが開放厳禁の内扉が深夜開いていたことから、コミュニティーに亀裂が走り出す…。
②何かがこの夜をやって来る
総指揮・主演はデビュー作「ギフト」で高い評価を受けたジョエル・エドガートン、制作スタジオは「ムーンライト」他先鋭的な作品を生み出し続けるA24。アメリカでは去年公開され批評家の受けは良い今作。最大の論点は「it/それ」とは何なのか?だろう。
初手ネタバレをしておくと、「何か」は一度も出てこないし正体も明かされない。何度も「病気」という語は出され、廊下に掛かった絵がブリューゲルの「The Triumph of Death」であるように、何らかの感染症であるとは言われる。だが私はこの「病気=it」はメタファーであり、見た目通り受け取るべきではないと考える。理由を幾つか提示していこう。
③itは病原体なのか?
・防疫ガバ
酷評レビューで多く見られたもの。会話を多少交わしただけのウィル相手にマスクを外し、ポリタンクに直に口つけて水を飲む。煮沸した湯で外出着を消毒することもしない。
防毒マスク・手袋・赤い内扉は物理的に病原体を排除するものではなくお前を拒絶するという意思表示を意味するものと私は考える。だからこそポールは、ウィルに信頼を寄せる間はマスクを外し、疑い出してからはマスクを着けるのだ。
・感染者を見せない
ポール一家の祖父バッドは冒頭で死ぬが、血色の悪さは老人としては普通だ。ウィル一家の息子アンドリューは感染するが、魘されだして以降は一度たりとも画面に顔を見せない。肌が真っ黒に壊死しボコボコと膨れる感染者のイメージは、ポール一家の息子トラヴィスの夢を通じてしか描かれない。
・感染者は「病死しない」
これがメタファーであると考える最大の理由。バッドは冒頭で安楽死させられた。森にかけこみ感染したと思しき飼い犬は、ポールとウィルの手で殺された。ネタバレになるが、ウィル一家3人も感染者だと判断され処刑された。今作、誰一人として病によって死ぬ者は居ないのだ。
④Itの正体と二つの映画
https://gaga.ne.jp/itcomesatnight/(シークレットレビューの項)
http://news.livedoor.com/article/detail/15630730/
公式サイトみたいに高尚ぶってはぐらかすのも愚かなので、私なりの解釈をはっきり言語化しよう。Itとは「悪(と他者が認識するもの)」である。見終わって浮かんだ映画が2本ある。「ヴィレッジ」と「イット・フォローズ」だ。
「ヴィレッジ」は森の奥に怪物が居る、だから小さな村の中で無垢に生きて行こうという話だった。大人たちが演じる怪物を振り切り駆け抜けた少女は、森の果てに広がる現代社会を見て呆然とする…という話だ。あの怪物と今作のitは似たものではないだろうか?
トラヴィスが何度もバッドの夢を見るように、思い入れのある祖父だったのだろう。ゆえに、義父であり異なる父権たる彼をポールは疎ましく感じたのかもしれない。アンドリューはトラヴィスと違い従順な子供ではない。夢遊病で内扉を開ける(=別の価値観を家の中に招く)彼を、ポールは感染者と見做した。ウィルの妻キムは若く性的魅力に溢れる。トラヴィスは彼女の胸や腿に目を遣り、夫婦の情交を盗み聞きしている。性に目覚めてしまった自分の息子まで、ポールは処分する。ラストシーン、ポール夫妻は互いを見つめる。その瞳は黒く染まり感染者の兆候を示している。我が子に手をかけてしまった自責と憎しみで、二人は視線を交わし合う。
では、Itは無くすべきものなのだろうか?A24の大ヒット作「イットフォローズ」のスタッフは、今作に大きくかかわっている。「イットフォローズ」の監督デビットロバートミッチェルは、ついてくるものは「愛と生と死」であると説明している。人と関わって生きていく上で、決して逃れ得ぬもの。だからこそ覚悟して、共に歩んでいかねばならぬ他者性。ヴィレッジの元ネタはブラッドベリの短編「びっくり箱」なのだが、閉鎖社会を飛び出し外部を知った少年が叫ぶシーンで小説は閉幕する。”僕は死んだ。死んだんだ。死ぬのはうれしい。死ぬというのは、なんてすてきなことだろう!”
⑤メタファーの傑作たち
ここまで書いてきてどうかと思うが、作品評価としては興味深い(interesting)が面白い(entertaining)とは言えないに落ち着く。理由を説明するために、メタファー映画の傑作を紹介しよう。
50年代、宇宙人映画はアメリカに忍び込んだアカを意味していた。ロメロの「ナイトオブザリビングデッド」は黒人差別、「ゾンビ」は商業主義の奴隷を意味していた。これらの映画が優れているのは、裏の意味を読み解かずとも映像的に楽しめるところだ。怪獣が核の象徴だと分からずとも、本田猪四郎の「ゴジラ」は涙が出るほど素晴らしい。「イットフォローズ」だって、ババアが摺り足でにじる画がクソ怖い。
⑥「見せない」映画
視覚的に怪物として現出させろ、という短絡的な発想ではない。ブツを見せないホラーはいくらでもある。「ねじの回転」は性的不満で苛立つオールドミスの狂奔ぶりが凄まじい。「ブレアウィッチプロジェクト」は後年「幽霊の出ないホラー」として批判されるが、異常な雰囲気で一行が散々に互いを罵り合うからこそ、あの映画は怖い。「10・クローバー・フィールド・レーン」は後半エイリアンパニックものに変わるが、前半の密室劇では「宇宙人が居ると言い張るだけの狂人ではないか?」というスリラーになっているのだ。
上述した通り、怪物が出ない以上はサイコスリラー・サスペンスにならざるを得ない。「イット・カムズ・アット・ナイト」はそこの作りが上手くないのだ。
⑦サイコスリラー
例えばItの恐怖を煽るのは森の風景や悪夢ではなく、人間の狼狽ぶりにするとかさ。
サイコもので見せ場になる筈の決裂過程も上手くない。赤い扉を開けた犯人捜しをあっさり済ませたのはもったいない。そこは互いの家族の人格否定を滲ませながらネチネチ粗探しようぜ!
あっさり「安全のために互いの居住空間を分けよう」としたのも味気ない。表面上は仲直りしていても会話の時に顔の位置をずらしたり、共有物を布越しに触れる描写を積み重ねた上で、決定的に断絶しなきゃ。このジャンルは胃がきしんでナンボでしょ!
⑧結びに
本作は本国での一般客受けがクソ悪く、日本公開は一年遅れた。ミニシアター限定の「意識高い系」映画に分類されるが、ホラーとしてそこそこのレベルにあるのでもっと知られるべき作品だと思う。高尚ぶって言辞を弄したり、やっぱクソ映画だ死ねーと罵倒したり。何だかんだ語る幅のある、コスパの高さは間違いない。